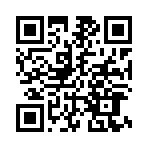と、ここしばらくの好天
と、ここしばらくの好天 で、道路の雪
で、道路の雪 もかなり溶けました。
もかなり溶けました。だけど、ブルが積み上げた雪
 の山はあちこちにあります。
の山はあちこちにあります。暖かいので、屋根の雪
 も溶け、つららになっています。よそ様の(家ですが)
も溶け、つららになっています。よそ様の(家ですが)今までは雪・雪・雪
 でモノトーンの世界でしたが、雪が溶け始めて、山にも色彩感がでてきました。 今週はお天気もよく、暖かい日
でモノトーンの世界でしたが、雪が溶け始めて、山にも色彩感がでてきました。 今週はお天気もよく、暖かい日 が続きそうです。
が続きそうです。このまま春になればいいのですが、まだ2月。 昨年も3月・4月に降雪
 があったので、まだまだ油断はできません。
があったので、まだまだ油断はできません。さて、色といえば、人間の目に映る色ですが、人間の目には錯覚というものがあります。 その錯覚(正確には視感度のずれ)をうまく利用すれば意外な色が目立つことにもなります。
友禅などに使われる伝統色のなかには、緑がかった茶色を「利休茶」、緑がかったグレーを「利休鼠(ねずみ)」と呼ぶなど、豊臣秀吉の寵愛(ちょうあい)を受けて茶道を大成させた千利休にちなんだ、わが国独特の色使いがあります。
といっても、利休が使いはじめたり、好んだりした色ではなく、抹茶の緑にちなんで後世の人が名付けたようです。
速水宗達(1740~1809)の「喫茶明月集」に、「宗旦は八十一に及て、紺の足袋をはきたり。 利休は浅黄の足袋をはきたり」と記されています。 浅葱(浅黄・あさぎ)色は青系統のやや緑みのある青色のことです。
利休は茶室のなかで、青い足袋を愛用したのはなぜでしょうか?
 これも色彩理論で分析してみると、利休のしたたかな計算が働いていることがわかります。
これも色彩理論で分析してみると、利休のしたたかな計算が働いていることがわかります。私たちは網膜の視細胞で色を感じていますが、明るい場所では赤が鮮やかに遠くまで見え、青は黒ずんで見えます。 一方、暗い場所では青が鮮やかに遠くまで見えるのに対して、赤は黒ずんで見えるのです。
これは、桿体(かんたい)と呼ばれる視細胞の働きによるもので、人の目は暗くなるほど青い色に敏感になります。 旧チェコスロバキアの生理学者 ヤン・エヴァンゲリスタ・プルキニェが発見した人間の目の働きで、「プルキニェ現象」と呼ばれています。
つまり、薄暗い茶室のなかでは、青い足袋が鮮やかに浮かび上がって見えるのです。

きっと利休はこのことに気付いていたのでしょう。 袱紗(ふくさ)については定かではありませんが、推測では浅葱(浅黄)色の袱紗を使いお茶をたてたと思うのです。
この話は、茶の湯をたしなんでいる方は一度は聞いたことがある有名な逸話です。 利休のしたたかな身のこなしが人を引き付ける魅力にもなったのでしょう。
また 明るいところでは真っ赤なバラの色が映えるのに、暗くなるとくすんでしまいます。 プレゼントの赤いバラは日中に渡すようにしましょう。 私たちもこうした現象をどんどん応用すべきだと思います。
例えば、照明を落とした会場でのパーティーなどに出席するのであれば、赤や白のドレスよりも、ブルーのドレスのほうが際立って映え、印象に残るはず これで夜のパーティードレスにブルーが多いのも納得ですね。

また プルキニェ現象による心理的影響として、夕暮時は人間の心理が不安定になりやすくなり、統計学上でもこの時間帯に衝動買いする人が多いと言われます。
人間の錯覚による色の不思議、奥が深いです。
尚、お時間がありましたら、こちらもどうぞ→「買い物難民」(アメーバ)、「穂高町営しゃくなげ荘」(楽天)