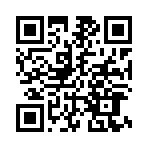の丑の日は「うな丼」、「うな重」ですね。
の丑の日は「うな丼」、「うな重」ですね。うなぎは古くから食べられていたらしく、万葉集にも読まれています。
石麻呂に我れ物申す夏痩せによしといふものぞ鰻捕り食せ
「うな丼」もいいですが、丼物といえば、「カツ丼」も捨てがたい。

カツ丼といえば普通 全国的には卵とじカツ丼をいいます。 卵とじカツ丼は、現在、日本で最も一般的なカツ丼ですね。
カツ丼は、戦後しばらく日本が貧しかった時代に庶民にとってはご馳走
 でした。
でした。その頃の刑事ドラマ
 の取調室のシーンにおいて、刑務所に行ったら二度と食べられないだろうと、刑事が自分の安月給から店屋物のカツ丼をとってやり、被疑者に食べさせるシーンがよくある。
の取調室のシーンにおいて、刑務所に行ったら二度と食べられないだろうと、刑事が自分の安月給から店屋物のカツ丼をとってやり、被疑者に食べさせるシーンがよくある。被疑者はその情にほだされ犯行を自供をする というモチーフがたびたびパロディ化され有名となり、本来は有り得ない事を特別にした。
というエピソードのはずが、「取調中の食事はカツ丼が出る」という風に誤解されていることすらある。
卵とじカツ丼の具は、玉ねぎとトンカツを割り下で煮て、溶き卵でとじたもの。 上に三つ葉やグリーンピースなどを散らしたり、それらを具と共に軽く煮る場合もある。
玉子丼や親子丼とよく似た料理法であり、親子丼の鶏肉をトンカツに変えた応用形とも考えられる。
そして 信州・北陸方面で有名なのが、ソースカツ丼。

「ソースカツ丼? トンカツにソースかけてごはんに盛るだけでしょ? 別にどうってことないじゃん!」なんて言っちゃうアナタ! それは大きな誤解です!

普通のカツ丼といえば、煮カツを卵でとじたものが、一般的なイメージ。 でも、ソースカツ丼は、煮たりとじたりしない。
熱々の揚げたてカツを、どっぷりとソースで味付けする。 まさに「ソース命」
 のカツ丼なのだ。
のカツ丼なのだ。信州では、「カツ丼」といえば、このソースカツ丼を指すのが当たり前
 なのです。
なのです。特に発祥の地として名乗りを挙げている長野県内の駒ヶ根・伊那の両市では、それぞれ「駒ヶ根ソースカツ丼会」、「伊那ソースカツ丼会」を発足し、「ソースカツ丼パイ」や「ソースカツ丼まん」を作るなど熾烈なPR合戦
 を繰り広げているという。
を繰り広げているという。このソースカツ丼の誕生は?というと、
「1921年(大正10年)に早稲田高等学院生の中西敬二郎氏らが考案、周囲の食堂
 から全国へ広まった説」
から全国へ広まった説」「明治時代にドイツ留学した高畠増太郎氏が、大正2年に東京の料理発表会で発表し、後に早稲田鶴巻町の自分の食堂
 のメニューとした説」
のメニューとした説」など諸説あり、長野の他にも福井や群馬、福島などに「ソースカツの地」を謳う町はある。
さて、肝心のソースだが、店では自家製を使うところが多いほか、各家庭でも「ソース+砂糖」、「ソース+醤油+砂糖」、「ソース+醤油+みりん」など、味はそれぞれ。
さらに、千切りキャベツを敷く場合もあったりなど、細かいバリエーションはいろいろあるが、共通していえるのは、ちょっと甘めのソースがよく染みている
 ことだろうか。
ことだろうか。食べ方にも個々にこだわりや流儀が結構あり、「カツを一度ひっくり返して食べる」方式が多い。
というのも、ソースのよく染みたたかつは当然美味いが、「ソース染み染み」の恩恵を、カツだけが独占するのはもったいない。
せっかくなら、カツを裏返し、表面に光る余剰ソースをごはんに染みこませてあげ、ごはんまでも立派な「ソース染み染みごはん」に変えてあげよう
 という理由である。
という理由である。また、「ソース染み染みごはん至上主義」の人などは、白飯と白飯の層の間に、ソースカツを敷き詰めるという秘技を行っていた。
一見「真っ白なご飯」をめくると、染み染みソースカツと、カツの周り中に染み染みごはんが、まるで宝探しのような心境である。
もちろんカツを主役として、惜しげなく食べるのも良い。 味が濃厚なので、普通のトンカツや卵とじカツ丼に比べ、冷めても美味しく、カツサンドにもピッタリ。

「卵とじ派」な人も、一度試してみて欲しい。 ソースカツの魔力に、きっとハマるはず。
たかが「カツ丼」 されど「カツ丼」 「カツ丼」は奥が深いのである。
尚、余談だが、受験生や試合に臨むスポーツ選手の「勝つ」
 というゲン担ぎのために、前日や当日にカツ丼が食べられる事がある。
というゲン担ぎのために、前日や当日にカツ丼が食べられる事がある。しかし カツは消化に時間を要するため、カツ丼を食べる行為は逆効果
 となる事がある。
となる事がある。

 at 2010年07月28日 11:33
at 2010年07月28日 11:33