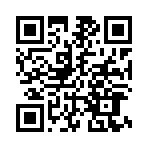シーズンでもありますね。
シーズンでもありますね。お墓参りに行く方も多いと思います。 お墓参りに欠かせないものといえば、お花とお線香。
日本では、お墓や仏壇にお供えとして、線香を燻らせることは欠かせません。
いつからこういう習慣が根付いたのか? 一般に用いられるようになったのは江戸時代以降 とされています。
日本に伝来した時期ははっきりしていませんが、聖徳太子の時代、推古天皇3(595)年 淡路島に香木「沈香」が漂着したと日本書紀に書かれています。
その後、各種の香木が中国から入ってきましたが、聖武天皇の時代、東大寺正倉院に納められた有名な香木「蘭奢待(らんじゃたい)」もそのひとつです。
そもそも、お線香を燻らせることは「仏様のお食事」や「自分の身を清める」という意味がありますが、「香りと煙を通じて仏様とお話をする」
 という大切な意味合いがあるのだそう。
という大切な意味合いがあるのだそう。尚、お供えする線香の本数は、一般的には1~2本ですが、各宗派で異なります。
浄土宗、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗は1本で、天台宗と真言宗は3本です。 香炉に立てるときは、まとめないで1本ずつたてます。
真宗大谷派と浄土真宗本願寺派は線香を立てず、線香を適当な長さに折って火をつけ、香炉に横に寝かせます。
ただ、正式には上記の通りですが、一般家庭ではあまり厳密に区別されていません。
現在 線香の生産は、全国生産の約70%のシェア
 を淡路島の一宮地区で占めています。 また 淡路島は国生みの神話が残っていることでも有名です。
を淡路島の一宮地区で占めています。 また 淡路島は国生みの神話が残っていることでも有名です。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冊尊(いざなみのみこと)は天津神より「天の沼矛(ぬほこ)」を授かり、
「この漂っている国土をあるべき姿に整え、固めなさい」という命を受け、「おのころ島」(現在の淡路島)という一つの島ができたと言われています。
線香は、香木や香料に松脂(まつやに)などの糊や染料を加えて練ったものです。
主な原料には、次のようなものがあります。
[白檀(びゃくだん)]
インド、東南アジアなどで産出する常緑樹で、特にインド南部産のものが良質で老山(ろうざん)白檀と呼ばれています。
木材そのものが香るため、仏像、数珠、扇子などにも使われます。 「栴檀(せんだん)は双葉より芳し」の栴檀は、この白檀のことです。
[沈香(じんこう)]
東南アジアに産出するジンチョウゲ科の樹木内に、長い年月を経て樹脂が蓄積したものです。 水に沈むので沈香といわれます。
[伽羅(きゃら)]
沈香の最上の種類。 ベトナムの限られたところから産出され、古くから品位の高い最上の香りと珍重されています。
そのほかの原料としては、椨(たぶ)、丁子(ちょうじ)、桂皮(けいひ)、大茴香(だいういきょう)などがあります。
お盆は線香を燻らせ、香りと煙を通じて仏様とゆっくりお話ををしましょう。



 at 2010年08月04日 09:57
at 2010年08月04日 09:57